今話題の「メルコジ」さん ― 2011/12/06 09:09
<画像引用>
Merkozy Frankreich und Deutschland sollen der Kern des neuen Europas werden - Politik Ausland - Bild_de
http://www.bild.de/politik/ausland/euro-krise/frankreich-und-deutschland-sollen-der-kern-des-neuen-europa-werden-21311112.bild.html
ユーロゲドンとダラーゲドンに猛追するはチャイナゲドン? ― 2011/12/07 07:52
<関連記事引用>
Debt crisis: In our competitive decadence, we face eurogeddon and dollargeddon
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/20/us-debt-crisis-european-default
China-geddon: A China crash will be scarier than Europe
http://www.firstpost.com/economy/china-geddon-a-china-crash-will-be-scarier-than-europe-146757.html
アイ・シャル・リターン 「南シナ海の縄張りを手放すわけにはいかない」=日経・秋田浩之 ― 2011/12/08 08:16

秋田氏が対中戦略の秘策をたずねたのは、今から約1年前のこと。
その時すでにダーウィン駐留が浮上していた。
<関連記事引用(画像も)>
マッカーサーの戦略なぞるオバマ大統領 編集委員 秋田浩之
2011/11/17 7:00
http://s.nikkei.com/t3FvxS
「第2次大戦中、旧日本軍にフィリピンを追われたマッカーサー司令官がどこから反攻したか知っているか」
これからの対中戦略の秘策をたずねたときのことだ。米政府当局者はにやりとしながらこう切り返し、答えを明かした。「オーストラリアのダーウィンだ」
アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を切り盛りした後、オバマ米大統領が息つく間もなく豪州に飛んだのも、そのダーウィンを訪れるためだった。米大統領として初の訪問だ。
たんなる結束のセレモニーが目的ではない。アジア太平洋の軍事力学を変えかねない重要合意を交わすため、豪州にやってきたのだった。
■精鋭部隊を豪北部のダーウィンに駐留へ
その合意とは中国軍の増強などをにらみ、米軍が第2次大戦後初めて、豪州に本格駐留するというものだ。精鋭の戦闘部隊として知られる米海兵隊を豪州北部のダーウィンに駐留させる。
2012年から200~250人の規模で部隊を配置する。最終的には2500人に増やすという。新たな基地をつくるのでなく、いまある豪州軍基地に米海兵隊が“同居”する方向という。
米豪の軍事協力を拡大するだけではない。米軍はこれから豪州への空母や艦船の寄港を増やすほか、共同の演習や訓練も広げていく。米安保当局者はこう予告する。
「これから米豪の軍事協力は目に見えてさらに加速するはずだ。よく注意して見ているといい」
これは中国軍の台頭をにらみ、米軍の態勢を立て直すための大きな布石だ。
オバマ政権は中国の軍備増強に対応するため、アジア太平洋への関与を強める方針をかかげている。しかし、米軍がいまアジアに持っている拠点は事実上、日本と韓国しかない。日本は約4万人、韓国には約2万8000人が駐留している。
これ以外では、対テロ戦を展開しているフィリピンに百数十人を派遣しており、豪州でもこれと同規模の米兵が駐留しているにすぎない。つまり、中国軍が進出しつつある南シナ海やその周辺には全くといって良いほど、自前の拠点を持っていないのだ。
新たに豪州に海兵隊の本格部隊が陣取ることになれば、この構図が変わり始める。米国は東アジアだけでなく、南太平洋にもいわば「不沈空母」を築く足がかりを得ることになるのである。
「豪州はたしかにアジアから遠いイメージがあるが、実は、北端のダーウィンは南シナ海から目と鼻の先にある。それは地図をみれば、一目瞭然(りょうぜん)だ」
米政府当局者はダーウィンの戦略的な重要性をこう解説する。
ここで時計の針を大きく戻し、第2次大戦当時の情勢を見てみよう。1942年3月、旧日本軍の猛攻を受け、マッカーサー司令官はフィリピンからの脱出を強いられる。そこで反攻の地に選んだのが、豪州のダーウィンだった。旧日本軍もダーウィンの戦略的な重要性を理解し、陥落させようと爆撃を加えた。
日本はその後、ミッドウエー海戦で大打撃を受け、戦局は米優勢に傾いていく。そうしたなか、反撃に出たマッカーサー司令官は44年、再び、フィリピンに戻ったのである。
■中国軍の活動目立つ南シナ海に足がかり
それから60年以上がすぎ、米軍が基地を持たない南シナ海では中国軍の活動が年々、目立つようになっている。
「アイ・シャル・リターン(私は戻ってくる)」。フィリピンから脱出した後、マッカーサーは屈辱をかみしめながら、こう誓ったとされる。この言葉を現代に置きかえれば、「南シナ海の縄張りを手放すわけにはいかない」となるのだろう。あたかもこの言葉をかみしめるように、米軍がダーウィンに駐留する。
<関連情報>
地政学を英国で学んだ:飲み会のメモ
http://geopoli.exblog.jp/17232226/
踏み絵を迫られた野田外交、訪中ドタキャン劇が示す中印冷戦ゲームの幕開け ― 2011/12/10 10:35
野田首相の訪中&訪印日程をめぐる水面下の駆け引き。
この外交ゲームが大きく動いたのは12月6日。
この日、読売は「訪印日程が12月27~29日の3日間とする方向で調整中」と第一報。この読売報道を受けて、おそらく中国は入手していた訪印日程情報が間違いないと確信。
そして同日、中国は野田首相の訪中日程延期を打診。
12月12日と13日の2日間の日程で北京を訪れる予定だった。
訪中延期を受けて「南京事件」影響説をまっ先に報じたのがNHK。
「歴史の溝浮き彫りに」とするNHKらしいリベラル・バイアス解説まで登場。
ここで注目すべきは中国が示した希望日程。
朝日によれば、12月28、29日の訪中を打診。
時事によれば、12月28日前後を提案。
つまり、訪印日程である12月27~29日に見事ぶつけてきたということ。
そこで日本政府は訪印日程と重なるため25日であれば可能と回答中。
「中国を取るのか、インドを取るのか」の踏み絵を迫られた日本政府。
踏み絵どころか中国による「訪印阻止作戦」にも見えてくる。
訪中ドタキャン劇が示すは中印冷戦ゲームの幕開け。
やる気満々のパンダさんとゾウさんはドジョウさんを困らせている。
<関連記事引用>
▼9月15日=首相 11月にも印訪問
2011/09/15 東京新聞朝刊 6ページ
野田佳彦首相は十四日、十一月にもインドを訪問する方向で調整に入った。シン首相ら政権幹部や経済界代表と信頼関係を築き、急成長を続ける巨大なインド市場への日本企業進出を後押しする狙い。複数の政府筋が明らかにした。アジア地域で影響力を強める中国の動向についても意見交換する見通しだ。
日本の首相がインドを訪問するのは二〇〇九年の鳩山由紀夫氏以来。戦略的関係の強化に積極的に取り組む意向を表明する。
▼9月20日=首相、12月訪印で調整
2011/09/20 産経新聞 東京朝刊 5ページ
【ニューデリー=早坂礼子】斎木昭隆・駐インド大使は19日、ニューデリー市内で日本商工会議所の岡村正会頭ら経済調査団と懇談し、12月上旬に野田佳彦首相がインドを訪問し、シン首相と会談する方向で調整していることを明らかにした。
両首脳は20日からニューヨークで開かれる国連総会でも同席するが、本格的な首脳会談は野田政権下で初めて。野田首相は訪印に際し、急成長するインド市場への日本企業進出を後押しする見通しだ。
首脳会談は、来年に両国の国交樹立60周年を迎えることから戦略的な関係強化に取り組む意向を確認。8月発効の包括的経済連携協定(CEPA)を踏まえインドの産業インフラ整備などでも意見交換する。日本の原発事故で中断している日印原子力協定締結交渉も議題にのぼるとみられる。
日印両国間では毎年、首脳が相互訪問することになっており、昨年10月にはシン首相が来日した。
▼9月24日=インド洋輸送路、日印が安保協力強化、首脳会談、首相、年内インド訪問。
2011/09/24 日本経済新聞 夕刊 3ページ
【ニューヨーク=黒沼晋】野田佳彦首相は23日午前(日本時間同日深夜)、ニューヨーク市内のホテルでインドのシン首相と約40分間、会談した。両首脳はインド洋のシーレーン(海上輸送路)の重要性を確認し、安全保障分野の協力を強める方針で一致。原子力エネルギーの協力についても、引き続き進めていく立場を確認した。
年内に野田首相がインドを訪問することも申し合わせた。原子力協力をめぐっては、シン首相が日本との協力の継続に意欲を表明。野田首相は「福島第1原子力発電所事故の原因を徹底的に検証して、迅速かつ正確に情報提供したい。そうした総括を踏まえながら協力を進めていきたい」と応じた。
国連安全保障理事会の改革や、11月にインドネシアで開かれる東アジア首脳会議に向けた連携も確認した。
両首脳は今年8月からの日印経済連携協定(EPA)の発効を受け、両国の経済関係をさらに拡大していく路線で足並みをそろえた。「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」や「インド貨物専用鉄道建設計画」の実現へ努力することも確認した。
インドは南シナ海への進出を加速する中国軍が、インド洋でも活動を強める事態を警戒。米国との安全保障分野での連携を探っている。野田、シン両首相が安保協力の強化で合意したのも、こうした動きを踏まえたものだ。
【ニューヨーク=黒沼晋】国連総会出席のため米国を訪れていた野田佳彦首相は23日午後(日本時間24日朝)、すべての外交日程を終え、政府専用機でニューヨークを出発した。24日夜に帰国する。
▼9月27日=首相訪中、来月下旬で調整、12月に訪印、訪米は来年の見通し。
2011/09/27 日本経済新聞 朝刊 2ページ
野田佳彦首相は26日、10月下旬に中国を訪問し、北京で胡錦濤国家主席や温家宝首相と会談する方向で調整に入った。昨年秋の尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件以来、冷え込んでいる日中関係を改善する契機にしたい考えだ。12月にはインドを訪問する見通しで、懸案となっている米国の公式訪問は来年1月以降になる方向だ。
玄葉光一郎外相と中国の楊潔〓外相は22日の米ニューヨークでの会談で、首相の年内訪中に向けて調整することで一致。来年の日中国交正常化40周年を前に、戦略的互恵関係の一層の深化を確認する狙いがある。
10月下旬以降に開く予定の次期臨時国会の日程によっては流動的な面もある。
中国外務省の洪磊副報道局長は26日の記者会見で、首相が戦略的互恵関係を深化させる方針を示していることに「注目している。各分野、各レベルで対話と交流、協力を積極的に強化していきたい」と述べ、早期訪中を歓迎する意向を示した。
インドとは首相の相互訪問を続けており、安全保障や原子力エネルギー分野での協力強化を確認する方向だ。
▼10月13日=首相12月訪中で再調整。
2011/10/13 日本経済新聞 朝刊 2ページ
野田佳彦首相は12日、12月下旬に北京を訪れ、胡錦濤国家主席や温家宝首相らと会談する方向で調整に入った。首相就任後初めての中国訪問で、戦略的互恵関係を深化させる方針を確認する。日中国交正常化40周年を2012年に控え、10年9月の中国漁船衝突事件後に冷え込んだ日中関係の改善につなげたい考えだ。
玄葉光一郎外相が11月に訪中。楊潔〓外相と会談し、首脳会談の日程や課題を詰める。首相は今月18日の韓国訪問前後の訪中を模索したが、日程が折り合わず再調整することになった。中国に続いてインドを訪れることも検討している。
▼11月16日=野田首相:12月12、13両日に中国初訪問で調整
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111116k0000m010151000c.html
日中両政府は15日、野田佳彦首相が12月12、13両日に中国を初訪問し、胡錦濤国家主席らと会談する方向で調整に入った。首相の訪中は、09年10月に北京で開かれた日中韓首脳会談に出席した鳩山由紀夫首相以来、2年ぶり。ただ、臨時国会(会期末12月9日)が延長された場合、変更になる可能性がある。
尖閣諸島沖の衝突事件などでぎくしゃくしてきた日中関係だが、来年は国交正常化40周年にあたることから、戦略的互恵関係を深化させていくことを確認する。また、東京電力福島第1原発事故を受け、中国が実施した日本産食品への輸入規制の解除や、研究段階にある日中韓自由貿易協定(FTA)の推進、東シナ海のガス田共同開発問題などを議論する見通し。
両国は毎年首脳の相互訪問を行っており、今年は日本が訪れる番。首相は訪中について、12月末のインド訪問、1月の訪米などをにらみ日程調整していた。官邸には「訪米後、戦略性を持って訪中すべきだ」との意見もあったが、首相は中国を刺激することを避け年内訪問を決断した。
これに先立ち、首相はインドネシアのバリ島で開かれる東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会合への出席に合わせ温家宝首相と会談する方向で調整している。9月の就任直後に電話協議したが、会談は初めて。【小山由宇、西田進一郎】
毎日新聞 2011年11月16日 2時30分(最終更新 11月16日 11時27分)
▼12月6日=首相の訪印、27~29日で調整 ★★★
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111206-OYT1T01042.htm
政府は6日、野田首相のインド訪問について、27~29日の3日間とする方向でインド側と調整に入った。
首相はシン首相と会談し、安全保障分野での連携強化や原子力協力の推進、レアアース(希土類)の共同開発を進めることなどを確認する見通しだ。
(2011年12月6日18時44分 読売新聞)
▼12月6日=首相の訪中延期 日程再調整へ ★★★
12月6日 19時35分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111206/t10014450571000.html
野田総理大臣は、就任後初めて、今月12日から中国を訪問する方向で調整していましたが、中国側から延期できないかという打診があり、日中両政府で協議した結果、訪問を延期し、日程を再調整することになりました。
野田総理大臣は、今月12日と13日の2日間、北京を訪れ、胡錦涛国家主席や温家宝首相と会談する方向で調整していました。そして、野田総理大臣も今月1日の記者会見で、「戦略的互恵関係を深化させるための具体的な議論をしていきたい。復興支援や観光促進などを話し合いたい」と抱負を語っていました。
こうしたなかで、6日までに中国側から、野田総理大臣の訪問日程を延期できないかといった打診があり、日中両政府で協議した結果、日程を再調整することになりました。野田総理大臣が中国を訪問する予定だった12月13日は、中国の南京で日中戦争中に日本軍が市民を殺害したり、暴行や略奪を行ったりしたとされる「南京事件」から74年の日に当たり、関係者は、訪問日程が重なるのを避ける意向があるのではないかとみています。
▼12月7日=首相の訪中延期、年内訪問で再調整 中国側が申し出 ★★★
http://www.asahi.com/politics/update/1206/TKY201112060528.html
野田佳彦首相は今月12、13日を軸に調整していた就任後初の中国訪問を延期した。中国側が打診してきた。日中両政府は年内の訪問実現へ再調整する。
外務省関係者によると、6日夕に丹羽宇一郎・駐中国大使が中国側から「内政上の理由で日程を再調整させてほしい」と伝えられた。詳細の説明はなかったが、13日が日中戦争で旧日本軍が南京を陥落させた「南京事件」の節目の日にあたるため、その影響に配慮した可能性があると日本側はみている。中国では今後の経済運営を話し合う中央経済工作会議の日程がずれ込む公算が大きく、その影響との見方もある。
野田首相は11月に仏カンヌで中国の胡錦濤(フー・チンタオ)国家主席と会い、年内の訪中で一致。両政府は正式発表していないが、首相が12、13日に北京を訪れ、胡主席らと会談する方向だった。ほぼ固まっていた首脳会談の日程が再調整されるのは珍しい。日本政府関係者によると、中国側は今月28、29日の訪中を打診してきているが、野田首相は同時期にインド訪問を調整している。2011年12月7日3時1分
▼12月7日=首相訪中延期 歴史の溝浮き彫りに ★★★
12月7日 4時5分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111207/t10014457271000.html
政府は、来週予定していた野田総理大臣の中国訪問を延期したことを受けて、日程を再調整する方針です。ただ、延期の背景には、訪問が「南京事件」の日と重なるのを避けたいという中国側の意向があったのではないかとみられ、歴史問題を巡る日中両国の溝の根深さが、改めて浮き彫りになりました。
野田総理大臣は、来週12日と13日の2日間、就任後初めて中国を訪れ、胡錦涛国家主席らと会談する方向で調整していましたが、中国側から訪問を延期できないかという打診があり、日中両政府が協議した結果、訪問を延期することになりました。
延期の背景について政府関係者は、12月13日が、日中戦争中に中国の南京で、日本軍が市民を殺害したり、暴行や略奪を行ったりしたとされる「南京事件」から74年に当たるため、野田総理大臣の訪問がこの日と重なることで、中国国内の反日感情が高まりをみせるのを避けたいという中国指導部の意向があったのではないかとみています。
政府は、野田総理大臣の中国訪問を、年内に実現させる方向で日程を再調整する方針ですが、ほぼ固まっていた総理大臣の外国訪問の日程が延期されるのは異例のことで、歴史問題を巡る日中の溝の根深さが改めて浮き彫りになりました。
政府は、日中国交正常化40年となる来年、両国の戦略的互恵関係を深化させたいとしていますが、関係の改善にあたっては、こうした歴史問題をはじめ、両国の国民感情の改善が課題になりそうです。
▼12月7日=首相、年内訪中で再調整 延期を正式発表
http://www.47news.jp/CN/201112/CN2011120701001054.html
藤村修官房長官は7日午前の記者会見で、今月12、13両日に予定していた野田佳彦首相の中国訪問の延期を正式に発表した。その上で、年内訪中に向け、両国間で調整を進めていると明らかにした。
藤村氏は「中国側も重要視しており、良い雰囲気の中で成功させたい。年内訪中で両国は一致している」と指摘。今月28日を軸に調整している首相のインド訪問より前に実現させたいとの意向を示した。
延期理由については、中国側が「内政上の事情」を上げたと説明。当初の訪中日程が旧日本軍による「南京占領」の日付と重なったことが影響したとの見方がある。2011/12/07 12:34 【共同通信】
▼12月7日=首相、今月の訪中延期…「年内」で再調整
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111206-OYT1T01125.htm
. 日中両政府は6日、野田首相が12、13日に予定していた中国訪問を延期することを決めた。
日本政府関係者によると、中国側が6日、北京の日本大使館に「内政上の都合」で延期を要請し、月内の別の日程を打診した。外務省幹部は「日程的に難しいが年内訪中で再調整したい」と語った。
13日は日中戦争で日本軍が南京を占領し、南京事件に発展してから74年にあたることから、中国の国民感情を考慮して中国政府が延期を判断したとの見方が出ている。年内の首相訪中は、11月12日、首相と胡錦濤国家主席との会談で合意していた。
(2011年12月7日01時09分 読売新聞)
▼12月9日=首相訪中、25日で最終調整=年内実現を重視 ★★★
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011120901108
日中両政府は9日、延期された野田佳彦首相の中国訪問日程について、25、26の両日とすることで最終調整に入った。複数の政府関係者が明らかにした。当初は12日から2日間とする方向だったが、中国側が延期を打診してきたため、両政府は年内実現を目指して再調整していた。
それによると、中国側は6日、「内政上の都合」を理由に延期を要請したものの、日本との関係を重視する立場から年内を希望し、28日前後を提案。しかし、首相のインド訪問と重なるため、日本政府は2012年度予算編成終了後と見込まれる25日であれば可能と回答した。
両政府は国交正常化40周年に当たる来年を前に首相訪中を実現し、戦略的互恵関係の進展を確認したい考えだ。(2011/12/09-21:47)
<画像引用>
夢をかなえるゾウ
http://amzn.to/sBDLyX
夢をかなえるゾウ 文庫版
http://amzn.to/uW7orq
バクバク・ゾウさんは世界最大の武器輸入国、ウハウハ・ロシアに続けと米国3番目のお得意様に ― 2011/12/11 08:56

<関連記事引用>
(WASHINGTON, December 3, 2011)
Fiscal Year 2011 Foreign Military Sales Exceed $30B
http://www.dsca.mil/PressReleases/by-date/2011/FMS_Sales_Exceed_30B.pdf
WASHINGTON, December 3, 2011- U.S. foreign military sales overseen by the Defense Security Cooperation Agency (DSCA) passed the $30 billion mark for the fourth consecutive year, with the fiscal year 2011 total reaching $34.8 billion.
Sales under the government-to-government Foreign Military Sales (FMS) Program were $28.3 billion, while sales executed by non-FMS cases managed under various security cooperation authorities were $6.5 billion.
The sales include cases signed by both the United States and our foreign partners through September 30, 2011. The top ten FMS customers for fiscal year 2011 were the Afghan Security Forces ($5.4 billion); the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States ($4.9 billion); India ($4.5 billion); Australia ($3.9 billion); Saudi Arabia ($3.5 billion); Iraq ($2.0 billion); the United Arab Emirates ($1.5 billion); Israel ($1.4 billion); Japan ($0.5 billion); and Sweden ($0.5 billion). DSCA forecasts FMS sales will continue to hover around $30 billion for fiscal year 2012, but official projections are still being calculated.
FMS and other security cooperation programs support U.S. national defense and foreign policy by helping our partners acquire the defense articles, services, and training they need to provide for their own defense and to be interoperable with the United States and partner nations during coalition operations.
▼インドが世界最大の通常兵器輸入国に ストックホルム国際平和研究所
2011.6.7 23:12
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110607/asi11060723140005-n1.htm
【ロンドン=木村正人】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は7日、2011年版年鑑を発表した。中国、インド、ブラジルなど新興国は力強い経済成長を背景に軍事支出を急速に増大させ、軍の近代化を進めている。中国やパキスタンとの緊張が増すインドは戦闘機や潜水艦の調達を進めるなど、この5年間で中国を追い抜き、世界最大の通常兵器輸入国となった。
同年鑑によると、10年の軍事支出は米国が6980億ドルで世界全体の43%を占め、2位の中国(1190億ドル、7・3%)を大きく引き離している。インドは413億ドル、2・5%で9位だった。
米国のほかに軍の近代化が目立つのは、中国、インド、ブラジル、ロシア、南アフリカ、トルコの6カ国という。こうした新興国の台頭に伴い、06~10年の世界の通常兵器取引高は01~05年より24%も増えた。
パキスタンとの間でカシミール問題を抱えるインドは、インド洋に進出する中国にも神経をとがらせており、戦闘機や潜水艦を調達して空・海軍力を増強している。05~09年の通常兵器輸入額では中国が世界全体の9%を占め1位、インドは7%で2位だったが、06~10年ではインドが9%、中国が6%と逆転した。
中国は自国製兵器の製造能力向上に努めており、軍事技術の盗用を恐れるロシアが中国への兵器輸出を抑えていることも中印逆転の一因になったようだ。
今年1月現在の核兵器数は米国とロシアの核軍縮交渉で前年より2070発減って、国連安全保障理事会常任理事国の5カ国とインド、パキスタン、イスラエルの8カ国で2万530個(推定)。インドとパキスタンはともに20発を増強したとみられている。
▼インド、兵器輸入で中国抜き世界一
2011年6月7日 10時01分
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-06-07_18881/
【ロンドン共同】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は7日、2011年版年鑑を発表、06〜10年の5年間の通常兵器輸入量でインドが中国を抜き、世界第1位になったことを明らかにした。
SIPRIは「インドは国内で治安上の問題を抱えるほか、隣国の中国、パキスタンとの競争が輸入増加の主な要因」と分析。専門家の間では、中国の輸入量減少は自国での兵器製造能力を高めているためとの見方が強い。
05〜09年の5年間では、世界全体の兵器輸入量のうち、中国が9%を占め1位、インドは7%で2位だった。しかし、06〜10年ではインドが9%、中国が6%と逆転した。両国とも最大の輸入相手国はロシアで、インドでは輸入量の82%、中国では84%を占める。
<関連記事>
India is third largest buyer of US arms
http://www.ndtv.com/article/india/india-is-third-largest-buyer-of-us-arms-156515
India becomes third biggest US arms purchaser
http://www.ndtv.com/article/india/india-is-third-largest-buyer-of-us-arms-156515
14 March 2011: India world's largest arms importer according to new SIPRI data on international arms transfers
India received 9 per cent of the volume of international arms transfers during 2006–10, with Russian deliveries accounting for 82 per cent of Indian arms imports.
http://www.sipri.org/media/pressreleases/armstransfers
日経:野田首相、面会上位に側近議員 官僚は外務・財務 ― 2011/12/11 09:56

<関連記事引用(画像も)>
野田首相、面会上位に側近議員 官僚は外務・財務
2011/12/10 23:48
http://s.nikkei.com/s4OSAG
野田政権は10日で発足100日を迎えた。この間に野田佳彦首相と面会した政治家をみると、上位は側近議員の名前がずらりと並ぶ。官僚は外務省や財務省の幹部が官邸をしばしば訪れている。
面会した政治家の上位は手塚仁雄首相補佐官、藤村修官房長官、長浜博行官房副長官ら。首相官邸に常駐する「地の利」に加え、首相とは気心が知れた間柄という事情もある。民主党側は輿石東幹事長が28回で首位だ。
官僚では事務のトップの竹歳誠官房副長官に次いで、警察庁出身の植松信一内閣情報官が2位に入った。国際情勢など様々な情報を定期的に報告しており、首相とは一対一で会うことが多い。
外務省の佐々江賢一郎次官や杉山晋輔アジア大洋州局長らも首相と2人きりで面会する機会がある。財務省は勝栄二郎次官らの姿が目立つ。欧州の債務危機を受け、中尾武彦財務官や木下康司国際局長の報告も増えた。
「政治主導」を掲げた民主党政権は当初、首相が官僚と会うときは政務三役の同席を義務付けていた。菅政権で慣例は崩れ、野田政権は官僚との距離がさらに近づいた。
日経・秋田浩之氏「真珠湾の埋もれた教訓(風見鶏)」 - 米国の国防長官や軍司令官らが大切にしている判断材料がある。それは歴史だ。 ― 2011/12/11 15:05
<関連記事引用>
真珠湾の埋もれた教訓(風見鶏)
2011/12/11 日本経済新聞 朝刊
約140万人の兵士を動かす米国防総省(ペンタゴン)。ひとつの判断ミスが、多くの人命を奪うことになりかねない。
では、国防長官や軍司令官は何をよりどころに作戦や戦略を決めるのか。側近の助言やインテリジェンスを頼りにするのは当然としても、もうひとつ、彼らが大切にしている判断材料がある。それは歴史だ。
「歴史局」(Historical Office)。巨大なペンタゴンの建物には、こんな風変わりな看板をかかげた部署がある。過去の軍事行動の失敗例や米軍が関与した国々の歴史などを調べ上げ、同じ過ちを繰り返さないようにするためだ。
ペンタゴンだけではない。陸、海、空、海兵隊の各軍にも歴史部局がある。「政策の決定にとって極めて重要な歴史の情報を軍首脳に提供している」(米陸軍)という。
米軍がそうした取り組みを始めたのは、第2次世界大戦の真っ最中の1943年だった。その教訓を次の戦いに生かすため、歴史家や地図の制作者らによる記録チームを立ち上げたのがきっかけという。
ひるがえって日本はどうか。近代の最大の失敗が、日本人だけで300万人以上の死者を出した第2次大戦であることは言うまでもない。70年前の41年12月8日、真珠湾を攻撃し、米国との戦いに突入した。
なぜ、勝ち目のない対米戦に向かったのか。
対中政策の誤算、ヒトラー、ムッソリーニと組んだ日独伊三国同盟の締結、米国の出方の読みあやまり……。吉田茂政権下の51年、こうした失敗を反省する文書はまとめられた。ところがその後、政府がさらに検証を進め、教訓をくみ取る作業をした形跡はない。
「日本は先の大戦で国を滅ぼす一歩、手前まで行った。外交も完全に失敗だった。しかし、どこで誤ったのか、政府としてきちんと検証しないままいまに至っている」
54年に外務省に入り、沖縄返還など多くの交渉にかかわった栗山尚一元駐米大使(80)は、自戒を込めてこう語る。「外務省で戦前、日独伊三国同盟を支持したといわれる人たちが戦後、幹部になっていた。これには違和感を持った」
その外務省にもひとつだけ、戦前の失敗を検証し、公式に総括した例がある。同省の不手際から開戦の対米通告が攻撃に間に合わず、英米などから「だまし討ち」の非難を浴びることになった一件だ。
これについては暗号を解読し、タイプに打つのに手間取った駐米大使館のせいにする見方があり、館員の遺族らは異議を唱えていた。そこで外務省が過去の文書を調べ「駐米大使館だけでなく、本省の対応も遅かった」という総括を90年代前半にまとめたという。
それにしても、どうしてこの程度のことに半世紀もかかるのか。このままでは大戦の検証はとてもおぼつかない。
「過去の失敗を総括するにはだれがいけなかったのかを特定し、事実上、名指しで糾弾しなければならない。日本にはそういうことを嫌う集団意識がある」。経緯を知る外務省の元幹部はこう打ち明ける。
仲間をかばおうとするあまり、戦争の失敗を検証できず、あいまいなまま時が流れていく。これは外務省にかぎらず、他の省庁や政治家、旧軍幹部、そしてメディアにも当てはまる。
戦争に敗れた日本は戦勝国の米国にもまして、どこで間違えたのか、じっくり検証する必要がある。同じ落とし穴にはまらないためにも、真珠湾の教訓に光を当てたい。
(編集委員 秋田浩之)
Merkozy Cartoon: タイタニックで戯れる「メルコジ」仮面夫婦の力関係 ― 2011/12/12 07:37
<画像引用>
about that Merkozy partnership…
Cartoon by Christo Komarnitski / Cagle Cartoons
http://www.thereformedbroker.com/2011/12/10/about-that-merkozy-partnership/
http://www.time.com/time/cartoonsoftheweek/0,29489,2101998_2327135,00.html


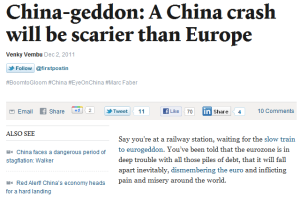


最近のコメント